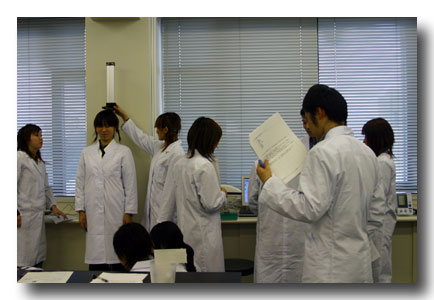この実習は、前半後半大きく二つのテーマを行います。
<学生の感想>
・レポートの提出は相当大変だったが、レポートの書き方や情報の収集・整理の仕方の勉強になる。世の中にあふれている栄養学情報を見る目が変わる。
・授業はパソコンで様々なデータを見て進みます。でもそのデータはレポートからのものなのでそのレポートがとても大変でした。
・インターネットやTV等での栄養情報に対しての感じ方が少し変わりました。逆に立場に将来たつ自分への責任感等改めて情報の難しさを実感しました。
・新しい授業科目だったので、いろいろ新鮮であった。前半はレポート提出で大変でしたが、良い経験でした。後半は自分自身の健康調査を行い、色々な体験が出来て楽しかったです。
・公衆栄養学実験Iでは科学的根拠を第一に考え、将来、一般の人に栄養指導を行う時に正確な事を伝える事が出来るのではないかと思います。また、授業中に骨密度や血流といった普段測る事がない検査を行いデータがもらえるので、自分がどういった健康管理をしていくべきかが分かって良かったです。